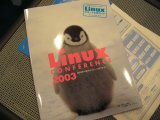Linux Conference 2003
一日目(10/30)
FLOSS-JP
 LC2003会場では筆記でアンケートに参加することができる。やらねばやらねばと思っていつつ、こたえそこねていたのでこの機会に参加することにした。ちなみに11月1日まで。
LC2003会場では筆記でアンケートに参加することができる。やらねばやらねばと思っていつつ、こたえそこねていたのでこの機会に参加することにした。ちなみに11月1日まで。
発表のほうでは中間報告を聞くことができた。
MACAO & FacePoint
 デモがおもしろかった。今のところ専用の機材がないとどうにもならなそうだけど、そのあたり、今後の発展に期待したい。
デモがおもしろかった。今のところ専用の機材がないとどうにもならなそうだけど、そのあたり、今後の発展に期待したい。
uim
(2003-11-04追記) T-Codeに対応していることで再び興味を持った。混ぜ書き変換とか部首変換とかができないと使いものにならないわけでなのだけど、話を聞くとやはりそこまでは対応していないようだ。Lisp系なのですぐに手を出せないとは思うけれど、注目はしておこう。
二日目(10/31)
Ruby/CHISE
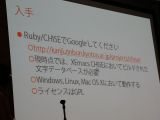 CHISE関係、特にRuby/CHISEのプレゼンテーションが印象的だった。漢字のへんやつくりのつながりのネットワーク図にしてぐりぐり。
CHISE関係、特にRuby/CHISEのプレゼンテーションが印象的だった。漢字のへんやつくりのつながりのネットワーク図にしてぐりぐり。
…というデモはKAGEも使っていたりするわけで、Ruby/CHISEだけでできるわけではないのだけど、とりあえずさわってみたくはなった。まずはモノを入手しよう。
三日目(11/01)
OpenPKSD
これはLCのほうじゃないけど、OpenPKSDの話を聞いてきた。興味深い。「Ruby、OpenPGPがわかる人、または根性のある人」を募集中とのこと。また、Pure Ruby版の開発に興味のある人、ML等の運用をしてくれる人、キーマージのバグを調査してくれる人を併わせて募集しているとのこと。
まずは時間をとって動かしてみるかな。
Lightning Talks
吉山あきらさんによるISABSの紹介からスタート。ISABSというのはバグ情報をもとに危険なサービスを(強制的に)止めてしまうためのフレームワーク。こういう作業というのはみんな個々にやってはいることなのだけど、システマティックに管理するというのはなかなかめんどくさい。そのあたりをうまく吸収してくれそうな可能性は感じた。ネックになりそうなのはバグ情報の更新だろうか。
お次は野首さん。Shinjuku BOFのクイズシステムで「戻る」ができないと指摘されたことを受けてのリベンジ——じゃあなくて、Flashプレゼンテーションのススメ。ちなみに今度はちゃんと戻れてた。これを見ていて、Ruby/SDLを使ったプレゼンツールを作りかけていたのを思い出した。またひっぱり出していじってみようかな。
次。杉浦さんによるVFS for Rubyの紹介。open-uriとかぶるものかと思っていたのだけど、そうではなかった。かなり高機能でよい。どんなことができるかというと、こんなことができる:
$ ruby -r vfs -run -e cp -- -r dir ftp://server.example.jp/dir/
これでdir以下のファイルを再帰的にftp://server.example.jp/dir/にコピーすることができる。また、次のようなコードで一時ファイルをWebDAV上に作るようにすることができる:
require 'vfs'
require 'tempfile'
t = Tempfile.new('tmp', 'http://localhost/tmp/')
いやーすばらしい。ほしくなったのでパッケージングしてみようかと思っている。
続いて近藤さんによるOpenOffice.orgのリリースプロセスについての紹介、朝木さんによるKDE-3.2の新機能についての紹介、かずひこさんによるフォント問題の総括。かずひこさんのプレゼンテーションではフォント問題で何が起こっていたか、またどういう点で問題が発生したのか、今後どうなるのか、どういう動きがあるのか——そういったことが分かりやすく語られた。
次の徳永さんたちはuim等のデモンストレーションをするはずだったのだけどマシントラブルで表示できず、キムチシェーキについての漫才に変更となった。続いては野首さんの二本目「オープンソースにみる勝ち組と負け組」。ある種のリベンジ。やはり真の勝者は彼であろう。たいそうおもしろかった。
最後は森本さんによるソースボーチという提案。Lightning Talks直前の1.5時間ほどを使って急遽作られたネタとは思えぬできで、これも非常におもしろかった。
追記(2003-11-04): よく考えるとVFS for Rubyのdebianizeは私がやる必要はないのかな。待っていればそのうちパッケージになっているにちがいない。
Ruby実践事例
LCのほうではないのだけど、まつもとさんのセッションを聞いてRuby実践事例に。発表された事例は四つ。なかむら(う)さんによるMS-Windows上のRuby事情の話、moriqさんによるMySQL/Ruby、ERB、mod_rubyを使ったCGIプログラムの実例、IkegamiさんによるMing/Rubyの紹介、福井さんによるRubyとFlashの連携事例の紹介。
普段MS-Windowsを使っていない私にとって、MS-Windows向けのバイナリの区別はよくわからなかったのだけど、なかむら(う)さんの話を聞いていろいろ分かった。moriqさんの発表は実際に使われている例が出ているという点でよかったのだけど、時間をオーバーしすぎかなあ。内容に関係して思い出したのだけどcgi.rbではnkfを使わないようにするって話ではなかったかしら。アレは結構困った感じなのだよね。
Ming/Rubyの事例としてはLightning Talksの野首さんの発表がある。Ming/Rubyもおもしろいと思うのだけどJaMingがベースにしているMingが古いとかいう問題があったりするようだ。ブラウザが必要だというのも、それはそれで困ることもあると思う。その次にもう一つFlash関係の発表が続いたわけなのだけど、こちらは時間が足りなかったのか、プレゼンテーションの内容をよく理解できなかった。発表された範囲で言えば、FlashとRubyの連携はなされていないように思えたのだが…。
全体としてみると事前の企画と現場での進行がまずかったかなという感じ。ざっと見渡したところ40人かそれ以上の人が集まっていたわけで、それくらいの関心を集めることができたわけだ。せっかくのチャンス(Rubyにとって、発表した人にとって、来た人にとって、など)なのだから、もう少しとりまとめのほうにもパワーを割いてほしかったように思う。